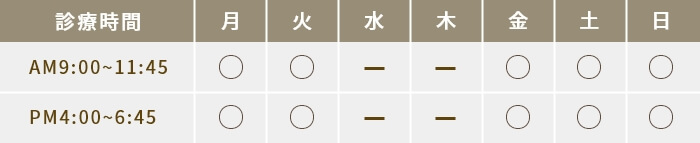お知らせ News
「抜歯ってかわいそう?」|獣医師が語る、愛犬・愛猫の歯科治療とおうちでできるケア
- 2025.05.23 | ブログ
皆さまは、愛犬や愛猫のお口の健康について考えたことはありますか?
実は、私たちと同じように、犬や猫も歯やお口のトラブルを抱えることがあります。
犬や猫は痛みを言葉で伝えることができません。痛みや異常があっても、それをものともせず元気にふるまう子が多いため、気づいたときには重症化してしまっていることも少なくありません。
そこで今回は、犬や猫によく見られる歯の病気とその治療法、そしてご家庭でできるケアについて、わかりやすくご紹介いたします。

■目次
1.犬や猫のお口の特徴と、歯の病気がもたらすリスク
2.犬や猫に多い歯のトラブルとその治療法
3.「これは良い!」と感じるおすすめの口腔ケア方法
4.サプリメントで手軽にできるお口の補助ケア
5.よくあるご質問|犬や猫の歯のケアについて
6.当院で行っている歯科治療について
犬や猫のお口の特徴と、歯の病気がもたらすリスク
◆犬や猫の唾液はアルカリ性|虫歯になりにくいけれど歯周病には要注意
人の唾液は中性からやや酸性ですが、犬や猫の唾液はアルカリ性のため、虫歯には比較的なりにくいといわれています。
ただし、アルカリ性の環境は細菌が繁殖しやすく、歯垢(プラーク)が歯石になりやすいという一面もあります。そのため、気づかないうちに歯ぐきが炎症を起こしたり、口臭が強くなったりする「歯周病」を引き起こしやすい傾向があるのです。
さらに歯周病が進行すると、歯ぐきの腫れや出血だけでなく、歯がグラグラになって抜け落ちてしまうこともあります。
◆進行した歯の感染症は全身の健康にも影響
歯周病が悪化すると、歯と歯ぐきの隙間(歯周ポケット)から細菌が血管に入り込み、全身にまわることがあります。
特に心臓の内膜や腎臓、肝臓などの臓器に炎症を起こし、深刻な病気につながるケースも報告されています。
つまり、歯の治療や毎日のデンタルケアは単に「お口の健康」を守るためだけでなく、愛犬・愛猫の健康を守るためにも、とても大切なケアなのです。
犬や猫に多い歯のトラブルとその治療法
犬や猫の歯の健康は、全身の健康と深く関わっています。ここでは、よく見られる代表的な歯のトラブルとその治療法についてご紹介します。
◆歯周病(ししゅうびょう)|最も多いお口の病気
【主な症状】
・口臭が強くなる
・歯ぐきが赤く腫れる
・よだれが増える
・ごはんを食べづらそうにする
【原因】
お口の中に歯垢(プラーク)や歯石がたまることで、細菌が繁殖し、歯ぐきに炎症が起きます。そのままにしておくと歯ぐきが下がり、最終的には歯が抜けてしまうこともあります。
【治療法】
まずは、スケーリングで歯石や汚れをしっかり取り除くことが基本です。
症状が進行している場合には、痛みや感染を防ぐために抜歯が必要になることもあります。
また、細菌の種類を特定する「細菌感受性検査」を行い、その結果に合ったお薬(抗菌薬)を使うことが大切です。
◆歯の破折(はせつ)|歯が折れてしまうトラブル
【主な症状】
・歯の一部が欠ける
・歯の色が黒ずむ
・噛むと痛がる様子を見せる
【原因】
とても硬いおもちゃや骨などを噛んだときに、歯が折れてしまうことがあります。犬や猫のエナメル質は人の約1/10の厚さしかなく、とても繊細です。
【治療法】
折れた箇所が神経に達している場合は、根管治療(歯の神経を除去して穴を埋める処置)で歯を残せることがあります。ただし、状態によっては抜歯を選ぶ方が負担が少ないケースもあります。
◆猫に多い吸収病巣(きゅうしゅうびょうそう)
【主な症状】
・歯の表面がボロボロになる
・ごはんを食べたがらない
・口を気にして前足で触るようなしぐさを見せる
【原因】
これは、猫に特有の病気で、歯の表面(エナメル質や象牙質)が体内の細胞により少しずつ壊されていく病気です。
詳しい原因はまだはっきりとはわかっていませんが、免疫の異常が関係していると考えられています。
【治療法】
強い痛みを伴うため、抜歯が最も効果的な治療法とされます。無理に残すとかえって苦痛が続くため、早めの判断が重要です。
◆歯の感染症と全身への影響
【主な症状】
・口や顔の腫れ
・鼻水やくしゃみ(特に犬)
・発熱や元気消失
【原因】
歯の根の周囲に感染が広がると、膿瘍(膿のかたまり)ができ、炎症が顔や鼻の奥にまで広がることがあります。特に上あごの歯が原因の場合、くしゃみや鼻水などの症状が出ることもあります。
【治療法】
感染の程度を調べ、細菌感受性検査をもとに適切な抗生剤を選択します。状態によっては抜歯やドレナージ(膿の排出処置)が必要になる場合もあります。
「これは良い!」と感じるおすすめの口腔ケア方法
愛犬や愛猫のお口の健康を守るうえで、最も効果が高いとされているのが歯磨きです。
とはいえ、いきなり歯ブラシをお口に入れようとすると、びっくりして嫌がってしまうことも少なくありません。
そこで大切なのが、歯磨きを「イヤなこと」ではなく「楽しい習慣」にしていくことです。
ここでは、はじめての歯磨きをスムーズに進めるための5つのステップをご紹介します。
<歯磨き習慣を身につける5つのコツ>
1.好みの味の歯磨き粉を見つける
チキン味やバニラ味、パン味など、犬や猫が「美味しい!」と感じるフレーバーの歯磨き粉を選びましょう。
2.指に少量つけて舐めさせる
いきなり歯ブラシを使うのではなく、最初はおやつ感覚で歯磨き粉を指につけてペロッと舐めさせることから始めます。
3.歯ブラシに歯磨き粉をつけて舐めさせる
歯ブラシに慣れてもらうために、次のステップでは歯ブラシに歯磨き粉をつけて舐めさせます。数日かけて、ゆっくりと慣らしていきましょう。
4.少しずつ、口の中に歯ブラシを入れてみる
慣れてきたら、歯ブラシをそっとお口に入れてみます。無理に進めず、愛犬や愛猫のペースに合わせてくださいね。
5.やさしく歯をこすって磨く
最後のステップでは、やさしく歯をこすって磨いていきます。歯ぐきを傷つけないように、力を入れすぎないことがポイントです。
慣れないうちは、歯ブラシを噛んでしまうこともあります。
そんなときは噛んでも壊れにくい歯ブラシを選ぶのがおすすめです。ペット用として安全性に配慮された歯ブラシも市販されていますので、使いやすいものを取り入れてみてください。
毎日のケアを無理なく続けていくことが、お口の健康維持につながります。
サプリメントで手軽にできるお口の補助ケア
これまでにお伝えしたとおり、犬や猫の唾液はアルカリ性のため、細菌が繁殖しやすく、歯垢が歯石になりやすいという特徴があります。
そのため最近では、唾液の性質にアプローチして、歯石の付着や細菌の増殖を抑える口腔ケア用サプリメントにも注目が集まっています。
特に、歯磨きが苦手な犬や猫、あるいは口に触られることに強いストレスを感じてしまう場合には、こうしたサプリメントを補助的なケアとして活用するのもひとつの方法です。
◆飲み水に混ぜるタイプ(液状サプリメント)
これは、私が獣医師として働きはじめた20年以上前から使われている、実績あるケア方法です。
飲み水に混ぜるだけで使えるので、無理なく続けやすいのが特徴です。安全性も高く、口臭の軽減や歯周病の進行をゆるやかにする効果が期待できます。
◆パウダータイプやタブレットタイプ
このタイプは、フードに混ぜたり、そのままおやつのように与えたりすることができます。
唾液のpHバランスを整えることで、歯石の形成を抑える働きが期待されており、日々のケアに取り入れやすいのが魅力です。
毎日の歯磨きに加えて、こうしたサプリメントを組み合わせていくことで、より自然な形でお口の健康を守ることができます。
愛犬・愛猫の性格や生活スタイルに合わせて、無理なく続けられる方法を選んであげることが大切です。
よくあるご質問|犬や猫の歯のケアについて
Q.骨や角を噛ませると、歯石が取れるって本当ですか?
A.一部こすれて落ちることはあるかもしれませんが、歯が折れるリスクの方が大きく、おすすめできません。
特に注意が必要なのが、硬い骨や角のようなおやつやおもちゃです。というのも、これらを噛んだ拍子に、歯が欠けたり折れてしまうことがあるからです。実際に、当院に「歯が折れてしまった」とご相談にいらっしゃるケースの多くは、こうした硬いものが原因となっています。
また、噛んで欠けた破片を誤って飲み込んでしまうと、窒息や腸閉塞など命に関わるトラブルを引き起こす可能性もあります。
歯の健康を守るには、毎日の歯磨きが最も安全で効果的な方法です。
すでに歯石が付いてしまっている場合には、動物病院でのスケーリング(歯石除去)を検討しましょう。
Q.抜歯ってかわいそうじゃないですか?
A.つらい思いをさせないために、あえて抜歯が必要になることもあります。
「歯を抜くのはかわいそう」と感じる気持ちはよくわかります。しかし、痛みや感染の原因となっている歯をそのままにしておく方が、結果的に苦しい思いをさせてしまうこともあります。
犬や猫は人間のように咀嚼して食べる動物ではないため、歯が少なくても適切なサイズのフードを与えれば問題なく食べられる場合がほとんどです。
犬や猫の歯には、皮や獲物を裂くための「切歯」、攻撃や防御に使われる「犬歯」、食べ物を小さく分ける「臼歯」といった役割がありますが、「すり潰す・噛み砕く」という機能はあまり重視されていないのが特徴です。
もちろん、健康な歯を大切に残すことは大前提ですが、「残すこと」にこだわりすぎず、愛犬や愛猫の体調や生活の質を第一に考えた治療を選ぶことが何より大切です。
Q.抜歯って「ぐりぐりして痛そう」なイメージがあります。
A.実際には全身麻酔下で丁寧に行うため、痛みを感じることはありません。
「ペンチのような器具で無理やり引き抜く」といったイメージを持たれることがありますが、実際の抜歯処置はずっと繊細で、動物への負担を最小限に抑えた方法で行われます。
具体的には、歯の頭(歯冠)をカットし、歯根をいくつかに分けてから、ひとつずつ丁寧に取り除きます。
抜歯後は1本につき小さな穴があく程度で、大きくぽっかりと空くことはほとんどありません。
通常、1週間ほどで自然にふさがるため心配は不要です。
Q.詰め物をしても、すぐ取れてしまいませんか?
A.歯が折れない限り、自然に取れることはほとんどありません。
詰め物には、中で広がって抜けにくい「ひょうたん型」の穴を使う技術が用いられており、しっかり定着するように設計されています。
さらに、多くの場合は光で硬化する専用のパテを使用するため、その日のうちからある程度の硬さのものも食べられるほどの強度があります。
ただし、小さな欠けや浅い穴では詰め物ができないこともあり、その場合は歯を残すのが難しく、抜歯を検討することがあります。
当院で行っている歯科治療について
お口のトラブルは、単なる痛みや不快感だけでなく、全身の健康にも影響を及ぼすことがあります。
当院では、愛犬・愛猫の体の状態や性格をしっかりと見極めたうえで、飼い主様と丁寧に相談しながら検査・治療方針を決定してまいります。
主な検査・治療には以下のようなものがあります。
◆抜歯
進行した歯周病や、歯が折れてしまった場合などに行います。
そのまま残しておくことで痛みや感染が広がる可能性がある歯を、必要に応じて丁寧に取り除く治療です。
◆根管治療(歯内治療)
歯の神経がダメージを受けている場合でも、条件が整えば歯を抜かずに残すことができる可能性があります。
「できるだけ歯を温存したい」というご希望がある場合に、選択肢のひとつとしてご案内しています。
◆細菌感受性検査
感染症が疑われる場合には、どの抗生剤が効果的かを調べる検査を行います。
その結果をもとに、より適切な治療薬を選ぶことが可能になります。
◆ウイルスPCR検査(猫)
猫では、歯肉炎や口内炎がウイルス感染と関連しているケースがあるため、必要に応じてウイルス検査を行います。
◆細胞診検査・病理組織検査
お口の中にしこりやできものが見られた場合は、腫瘍や他の病気の可能性を調べるための検査を行うことがあります。
早期に確認することで、治療方針の選択肢が広がる場合もあります。
「最近、食べにくそうにしている」「お口のにおいが気になる」など、ちょっとした変化が、実は病気のサインであることもあります。
歯科治療は、痛みをやわらげるだけでなく、愛犬・愛猫の健康寿命を支える大切なケアのひとつです。
ご不安なことがありましたら、どんなことでもお気軽にご相談ください。
福岡市東区のみどりが丘動物病院